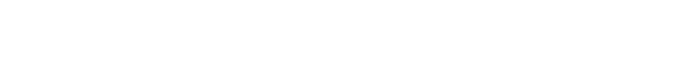ヒコロヒーの妄想小説「惨めなのは、コップの水を引っ掛けられた方か、引っ掛けた方なのか」
注目のピン芸人ヒコロヒーさんのコラム、スピンオフ! かがみよかがみに寄せられるエッセイのなかから、ヒコロヒーさんがインスピレーションを受けたテーマを「お題」に、妄想小説をお届けします。今回のお題は「二人だけの記憶」。二人だけの思い出として刻まれた場所、時間、ちょっとした会話。そんな過去をふと思い出したとき、今の私と同じようにあの人も思い出すことがあるのだろうかと、思いを馳せる。でもそれは、私と同じ風景なのだろうか?
●ヒコロヒーの妄想小説:本日のお題「二人だけの記憶」
「あ」
思わず声が漏れたのは、思い出す余地もないほど些細な記憶の蓋がふっとずれるようにして開いたからだった。
大輔とたった一度だけ、それも確か30分程だけ滞在したその小さな喫茶店の外観は、街馴染みが良すぎてその店だとはほとほと気づかぬまま通り過ぎそうでさえあった。
それは小田急線の沿線を遠くまで歩いてみようかと大輔と散歩していたら道すがらにあらわれた喫茶店だった。軒先に大小さまざまな植物が置かれてある以外は喫茶店とも分かりづらい、あまりにも地味な外観だったのだが、大輔は「雰囲気いいじゃん」と機嫌良さげに言って重たそうな黒い木製の扉をゆっくりと開けたのだった。
よみがえった記憶に導かれて、彼のように喫茶店の扉を開けた
大輔のことを思い出すのは彼が当時住んでいた豪徳寺を過ぎる時だけかと思っていたけれど、その沿線にも細やかな思い出が散らばっていた。それはまるで砂利の中に色の付いた細かな石が数点混じっているようで、この色に気がつくことさえなければ記憶の蓋は永久に閉じられたままだったのだろうと思えるが、この記憶の蓋というのはいかんせん錠が甘いらしい。ふとした拍子に、ほとんど事故のように、いとも簡単に開いてしまう。
仕事の打ち合わせのため普段は来ないこの街に来るなり大輔の事を思い出すことはなんとも不思議で、ふと時を計算すれば別れてもう4年になるらしかった。
時計を確認すればあと30分ほどは打ち合わせまでの時間があり、私はあの時ときっと何も変わっていないのであろう重たそうな扉をぐっと押した。
彼と過ごしたささいな日常の記憶。いまも宝物のように思っている
「お待たせしました」
おばさん、と言っても、お姉さん、と言っても怒り出しそうな絶妙な雰囲気の女性店員が無愛想にホットコーヒーを目の前に置く。金縁の薄いティーカップには金魚の絵柄がついており、あまり良い趣味だとは思えなかったけれど、こんなんだっけかな、と曖昧にしてほぼ初対面の気持ちでコーヒーを一口飲んだ。
少し酸味が強すぎるブレンドな気もすれど、こういう喫茶店でコーヒーの批評をすることほど野暮な事はない。温度は適温なのだから十分である。
ここで大輔とどんな話をしたのかと思い出そうにも、なかなか具体的なことは思い出されなかった。きっと私たちのことだから美味しいとか熱いとかオムライス食べてみたいとか、そんな他愛のないことのみだったのだろう。
大輔はせっかちだった。ラーメン屋に一緒に行っても自分のスピードで食べ終わると私がまだ食べていても平気で店の外へタバコを吸いに行き、運転すれば黄色信号はもちろん走り抜けようとするし、間に合わず赤信号になると舌打ちをしていた。映画の予告編はつまらないと言って必ず上映時刻の10分後からしか映画館に入りたがらなかった。
今思えば彼の何が良かったのかよく分からないけれど、それでも27歳の頃の私は年下の大輔に好かれたくて必死だった。悲惨な別れ方をしたような気もするけれど、今となっては大昔の話で、何かいい思い出になっているような気さえしている。
時々、別れた恋人のことを恨んで悪く言っている人に遭遇するが、それほどばかげていることはないと私は考えている。大輔はとにかく変な人で、迷惑をかけられたことも大変な思いをしたことも惨めな気持ちになったこともあったけれど、それも含めて彼と過ごした時間を私は宝物のように感じている。恋人関係というのはそういうものであるべきだと考えられて、一度でも愛し合った人のことを悪く言うのはナンセンスに思えて仕方がない。
ふとテーブルの上に置かれたもう一つの飲み物、水が入ったプラスチックの小さなコップが目についた。喫茶店で恋人を恨んでコップの水を引っ掛ける行為を今の若い子たちは知っているのだろうかと考える。果たしてコップの水を引っ掛けられた方が惨めなのか、それとも引っ掛けた方が惨めなのか、しばし考えてみたもののこれは経験者にしか分かり得ないことだと考え止めた。
聞こえてきたのは間違いなく彼の声。運命的と思える再会だった
「九段下にいいところがあってさ」
「遠いなちょっと」
店のドアベルと共に背後から会話している男性の声が聞こえた。いらっしゃいませ、という女性店員の声を遮るようにして彼らは喋り続け、私のふたつほど後ろの席に座ったように感じられた。間違いなかった。片方の男性は大輔だった。
振り返る勇気はなく、声と話し方のみで判断するしかなくも、「シ」を「si」ではなく「shi」と発音するあの少し鼻にかかった声は、紛れもなく大輔だろうと思え、全神経が一気に自分の背中に集中していくのがわかった。
これを人は虫の知らせと呼ぶのだろうか。こんな事ってあるのだろうか。大輔は豪徳寺に住んでいたけれどもしかすると沿線上で引越したのかもしれない。
「んはは」
背後から笑い声が聞こえ、心臓がどんと太鼓バチで打たれたような気になった。鼻から抜けるようなあの笑い方はどう考えても大輔の笑い方で、4年ぶりの再会が導かれるようにして入ったこの喫茶店とはあまりにも運命的に思えてならず、脈がどんどんはやっていくことを自覚せざるを得なかった。
大輔に未練がある訳でも、復縁したいと思っていた訳でもないけれど、ひとつ笑顔で挨拶でもすればもしかすれば何かの歯車が動き出すのではないかと考えれば胸の鼓動はたちまち大きくなっていった。
彼は私のことを話し始めた。彼はきっと、この店を覚えていない
「エリは微妙だね、あいつおっぱいちっちゃいんだよな」
背後から聞こえる大輔の声、話し方は、あの時と何も変わらないままだった。
「ええ、エリちゃん可愛いのに」
「可愛いけどつまんねんだよな」
「元カノいけば?」
「元カノいくほどモテなくねえから」
相手の男は「そうかあ?」と笑い、大輔は「元カノねえ」と呟いた。
「弥生って覚えてる?俺より3つ上の。なんかダサい女だったよなぁ。ぱっと見エロそうな感じしたけどわりと大した事なくて。ほら俺ってメガネのブス好きな時期あったじゃん、メガネのデブス専の時期。あいつ謎に俺の事めっちゃ好きだったし別にいっかなって感じで付き合ってたんだけど、重くてだるくなってきてさ、脇毛の処理も甘くてキモかったわ。なんか妙に不思議ちゃんだったし、スピリチュアルみたいなのとかも信じがちで、何かにつけて運命って騒ぐから怖かったんだよな。あ、金も借りてたけど1円も返してない。なのに何も言ってこねえから都合は良いよな。別れ際も『色々あったけどありがとう』って言われて。いい女って感じ。いやいい女っしょ。都合いいのがいい女だべ」
そう言って大輔は「んはは」と笑った。一瞬にして身体中の血流がぴたりと止まる、否、凍てつく、という感覚に陥った。彼はまさかその店内に弥生がいるとは思ってもいない、気づいてもいない、私とこの店に来たことさえきっと覚えていない。一年経たずして別れたけれど、私はその期間は幸せだった気がしていた。私がありがとうと連絡をした時、こちらこそありがとう、としおらしく返信をしてきたことも覚えている。
「大輔」
気がつけば大輔の席の前に立っていた。大輔が私を見るその目は、何か不潔で汚らしく気持ち悪いものを見るような目つきだった。
気がつくと、彼の前に立っていた。そして水の入ったコップを手に取った
「友達の前で些細な見栄張って楽しいかな?あんた3万はきっちり返してきたじゃん。私が愛想尽かした時には泣きながら土下座してたよね?別れたくない弥生といたいって、王将の前でさぁ。あんたこそ別れ際にありがとうとか中2みたいな返事してきたよね、なにしらけたふりしてくれてんの?大体、てめえのセックスがずっと下手だったからいけねんだろうが。こっちは優しさで言わなかっただけなのに何を棚に上げちゃってくれてんの?あんたとセックスすればするほど演技力上がっちゃってしょうがなかったんだけど。最終的にあんたのこと騙しきれてんだから私も大したもんだわ、エリちゃんのこともその調子で大女優に育てあげたら?どうせめちゃくちゃ芝居してもらってんだから。それで呑気におっぱいちっちゃいじゃねえんだよ。言っといてあげるけど、あんたのセックス何もかもズレてるよ。大体、乗れもしねえのにファッションでスケボー持ち歩くのも、車の運転荒いのもダセーんだよ。で、誰が不思議ちゃんだって?」
ぱしん、という破裂音のようなものと共に、私が手にしたコップの水は大輔の顔を強く打った。か細い声で何すんだよと呟く大輔の声が聞こえた気がした。
「それに人間なんだから毛生えて当たり前だろ」
私はそう言って猛烈な勢いで千円札をレジに置いて店を飛び出した。扉の向こうは、30分前と何も変わらない、ただの街並みが広がっており、拭い去るようにめいいっぱいに駆け抜けることに必死だった。
コップの水を引っ掛けられた方が惨めなのか、引っ掛けた方が惨めなのか、やはりこれは、経験者にしか分からないみたいだった。
息があがって足を止めた先にはドラッグストアが賑やかしく佇んでいた。
「くそ、ヴィーナス高ぇんだよ」
ヒコロヒーさん初の小説集「黙って喋って」1月31日発売
ヒコロヒーさん初の小説集「黙って喋って」が1月31日に発売されます。「ヒコロジカルステーション」で連載中の小説を加筆し、さらに書き下ろしも。朝日新聞出版。1760円。
詳細はこちら