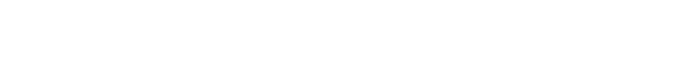ヒコロヒーの妄想小説「彼氏の女友達への感情。嫉妬なんて言葉では片付けられない」
注目のピン芸人ヒコロヒーさんのコラム、スピンオフ! かがみよかがみに寄せられるエッセイのなかから、ヒコロヒーさんがインスピレーションを受けたテーマを「お題」に、妄想小説をお届けします。今回のお題は「彼氏の女友達」。「そういうのじゃないんだって」という彼氏の気持ちもわかる。だけど、「そういうの」ってなに?あなたにとって、大事だからあえて「そういうの」にしないんじゃないの?「嫉妬」なんて簡単な言葉で言えたら楽なこの感情、ヒコロヒーさんが描きます。
●ヒコロヒーの妄想小説:本日のお題「彼氏の女友達」
「青井とはただの友達だって何回言えば分かんの?」
拓也は鬱陶しそうに眉間に皺を寄せてそう言って、持っていたマグカップを雑にテーブルに置くと、ごん、という鈍くて重たい音が狭いリビングに鋭く響いた。
私の恋人は、自分で苛立ちを抑えようとする時に必ず瞬きが長くなる。閉じている彼のまぶたのあたりにその怒りがじわあと滲んでいき、それが垂れ流れることのないように目に力を入れることで留めているようにも見える。そして、その不快などどめ色の感情、全てを身体中から抜くようにして鼻からゆっくりと息を逃していく。
あからさまに私に幻滅し、呆れていることが嫌というほどによく分かるその態度が悲しくて怖くて、自分でも制御できないうちにいつもとめどなく涙が出てきてしまう。「俺、公香に心配させたくないから青井とも会わせてるんじゃん」
拓也は小さな箱から背の低いたばこを取り出してそう言ったけれど、私は何も言うこともできずただ溢れてくる涙を拭い続けるしかなく、そのうちいつもの加熱式たばこの独特な匂いが鼻をかすめた。
「何が不満なの?俺は女友達も作っちゃいけないの?」
「…そういうこと言ってるんじゃないじゃん」
「なあ、俺、お前のために青井と会う時いつもお前を誘ってるんだけど」
「私のためじゃない、なんか、私への対策をしてるように見える」
「対策ってなに」
ずっといびつな警告音が鳴っている。私よ、止まれ
テーブルを規則的に中指で叩く音が張り詰めていく。拓也の感情は回し車のようで、加速すればするほど中にいる自分はハムスターのごとく身体のバランスを取るために、否が応にもそのスピードに合わせて自分の感情も加速させていってしまう。
自分が止まればいいと分かってはいるのに、それでも動き続けるこの足も、同じスピードで回転していく回し車も、もう急に止まることの方が出来なくて、こうなるともうだめだと、危ないと、後頭部の後ろあたりでずっといびつな警告音が鳴っているのに、やっぱり、と、狼狽えているのに、全てが相反していく。
「なんで私が青井さんといつも会わなきゃいけなかったの?」
「何?お前も青井のこと好きだっつってたじゃん」
「それは拓也の友達だからで、ていうか私、そう言うしかなくない?」
「そう言うしかないってなんだよ」
「私が青井さんのこと悪く言ったら拓也は私のこと絶対に軽蔑するじゃん」
「は?じゃあ何、お前が青井のこと良い奴だとか優しいとか好きだとか言ってたの嘘だったの」
「嘘とかじゃなくて、普通に、全然好きじゃない。ずっと、ずっと全然、好きじゃなくて、嫌だったよ、ずっと嫌で、青井さんも、青井さんといる時の拓也も、全部嫌で、全部嫌いだった」
ああ、もう、ああ、だめだ、と、分かっているのに、口から飛び出す言葉は、制そうとするもう一人の私の手をがむしゃらに振りほどいて勢いよく飛び出してはどこかしこへと散っていく。
拓也は呆れた表情で私を一瞥して、また鼻から息を抜くように吐いて、その吐き出された息は小さな蛇の大群に姿形を変えて私の眼球に絡みつき纏わり、目は刺すように痛く、なお染みるようにも痛く、なす術のない激痛にただ支配されるしかなかった。
あの人に初めて会った時、気付かないわけにはいかなかった
「公香ちゃんって本当にかわいいね、女子アナみたい。あ、宇垣ちゃんに似てるよね、拓也がずっとかわいいってうるさかったんだよ。飲むたび公香ちゃんの話してて。えっ、何この謎の甘い匂い、あ、クロエでしょ、なんかモテる匂いだ、かわいいなあ、女の子って感じ。私?私は香水とかつけないの」
初めて青井さんに会った時に言われた言葉や彼女のさばけた振る舞いからずっと逃がしてもらえないままだった。
ボブの艶やかな黒い髪を自信ありげにかきあげながら、飾り気のないTシャツとジーパン姿で、だるいとかキモいとか聞き感触の良くはない言葉を多用しつつも、さっぱりしている口ぶりゆえか会話に不快感がある訳ではなく、ビールを勢いよく飲み、おかしな時は大きく手を叩いて口を開けて豪快に笑う青井さんには、爽快感があった。
青井さんがトイレに行っている間「青井さんって拓也から聞いてたのとイメージ違ったからびっくりした、綺麗な人だね」と言えば「え?あいつ出っ歯じゃん」と言って拓也は意地悪く笑った。
確かに青井さんの大きな口元は特徴的だけれど出っ歯だなんて全然そんなことはなくて、むしろ大きめの前歯は小動物のようで魅力的だったし、やや上を向いたすっとした鼻は愛らしく、目も大きく、流行的なマットメイクは似合っていて、出っ歯じゃん、なんて、なぜ拓也が青井さんのことをそんな風に言わなければならないのか、よく分からなかった。
「ねえ、会社からダッシュで来たら髪の毛こんな状態なんだけどやばくない?実験失敗後なんだけど」
自身の乱れた髪を指しながらあっけらかんと笑う青井さんに、拓也は「やばいよお前、確実に何か爆発させてる」と笑っていたけれど、私は青井さんの描き足された眉毛も、重ね塗りされたアイラインも、浮いていないファンデーションにも、気付かないわけにはいかなかった。
「そういうの」な私と、「そういうの」じゃないあの人。あなたはどっちが大事なの
「なあ公香、青井とは本当にそういうのじゃないんだって」
「そういうのじゃないって言うのも、ずっと気持ち悪い」
「何なんだよそれ」
「『そういうの』って何なの?青井さんは『そういうの』じゃなくて、私は『そういうの』なの?」
「だからそういう関係には絶対にならないんだって、何回言えばいいの?」
「そういう関係にはならない、そういうんじゃないって、まるでそっちの関係の方が尊くて、価値があるみたいな言い方しないで。私は彼女じゃん、私は『そういうの』じゃん。今まで拓也の人生に何人もいた『そういうの』なんだよ。でも青井さんの、そういうのじゃない枠っていうのは、青井さんしかずっといないんじゃん」
「いやマジで、枠って何なんだよ。公香お前おかしいわ、落ち着けって」
「落ち着いてるよ、ずっと落ち着いてる。拓也は私より青井さんとの関係の方が大事だと思ってるんだって」
「いい加減にしろよ、話になんない」
お互い好きだけど「恋人にならないことに価値がある」ってこと?
「ずるいよ青井さん。そういうんじゃないって言葉に守られながらずっと拓也の側にいられるじゃん。私だってこんな姿、拓也に見られたくないよ。でも恋人になった以上、幻滅されて、呆れられて、怒らせて、傷つけて傷ついて、拓也に嫌われたとしても仕方ないじゃん。でも青井さんは、ずっと拓也に幻滅されることもないまま、ずっと拓也にとって大事な人でいられてるじゃん。これからもずっとそうなんだよ。交わらないように気をつけながら、大切にしながら、平行線描いてくんでしょ。それって何なの?拓也にとって青井さんって、不可侵領域みたいなことになってるんじゃないの?青井さんもそれを分かってるじゃん。訳わかんない理由つけて、そういうんじゃないとか言ってるけど、拓也も青井さんもずるいだけだよ。お互い恋愛対象として見てて、お互い好きなのに、この関係の価値は、恋人にならないことにあるって、恋人にならないから価値があるって、『そういうの』に成り下がることに緊張してるだけじゃん」
「公香マジで待って、あのさ、俺が好きなのは公香なんだよ」
「拓也は気付いてないふりしてるだけで、青井さんのことも好きなんだよ。分かってる」
「そういうんじゃないって」
「もう無理だって、別れよう」
「…マジでお前もういいって」
言葉も涙も止まらない中で堰を切ったようにごった煮な言葉が溢れ出て、私を拒絶したがっている鬱陶しそうな恋人の顔が目の前にあって、こんなこと言いたくなかった、そんな顔見たくなかった、そう思う度に、青井さんはこんなことをしなくても拓也の側にいられているという事実が首のあたりをちくちくと指し襲ってきて、痛くて痒くて、より一層また涙が溢れて、もう逃げ出してしまいたかった。
「青井とは本当に何もない、何もないから」
「…それが嫌、セックスでもしといてくれたほうがまだ良かったんだよ」
「する訳ねえじゃん」
「そういう関係になっててくれた方が、私はまだ良かったんだってば」
「意味分かんない。あのさあ、青井なんかに嫉妬することないじゃん」
「嫉妬できれば良かった、でも私、嫉妬もできないんだよ」
「…分かった、もう青井とは会わないから。ごめん」
そう言って拓也は痛そうに瞼をゆっくりと閉じてみせて、私は頬に張り付いた雫を拭うのに必死で何も言えなかった。
青井さんと会われることが嫌なんじゃない。拓也にとって自分の他に大事にしたい女性がいるということを、違う形で大事な女性が付かず離れずずっと拓也の側にいることが到底受け入れられなかった。
嫉妬という二文字で片付けられるような感情だったら良かった、浮気だと責めることができれば良かった、でも私は拓也と青井さんの関係を私はずっと責めることもできず、傍観するしかなかった。奇妙な拓也の口ぶり、化粧直しを施した青井さんの眉尻、小さいけれど確実な違和感は、拓也が青井さんの話をするたびに私の中で苔の如く増えてぬかるんで汚く広がっていった。
私とあなたは「恋人」だけど、あの人とあなたの関係は何なんだろう
「公香、ごめん、ちょっとこっち来て」
そう言って私の恋人は私の髪に触れる。涙でべちゃべちゃになってしまった私の顔周りの髪を優しく撫でてくれる。私の恋人は優しい。彼は私の恋人で、でも彼と青井さんという女性の関係の名前は、何なんだろうか。
疲れたように何度もごめんと呟く拓也の優しさと愛情を染みるように感じながらも、きっとこれからも私たちは彼女の存在に縛られるのだろうということも確かに感じて、また息がうまく出来ないほどに泣くしかなかった。
ヒコロヒーさん初の小説集「黙って喋って」1月31日発売
ヒコロヒーさん初の小説集「黙って喋って」が1月31日に発売されます。「ヒコロジカルステーション」で連載中の小説を加筆し、さらに書き下ろしも。朝日新聞出版。1760円。
詳細はこちら